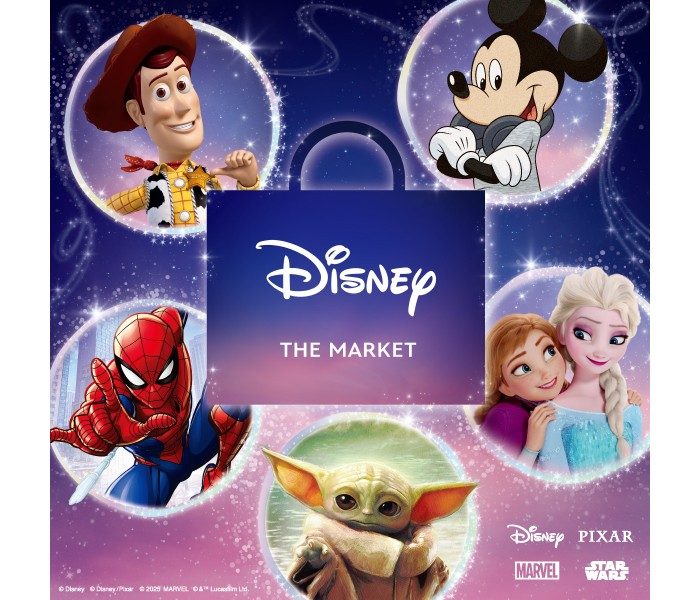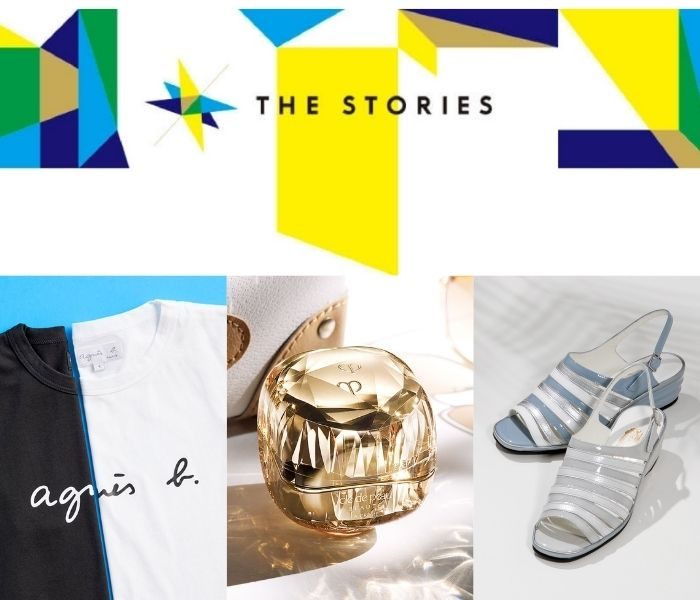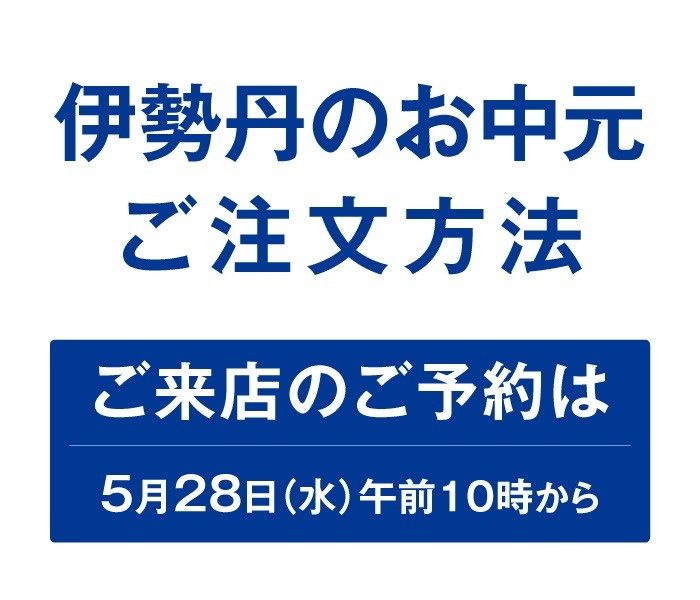日常から消えた道具を、ふたたび暮らしの中へ。<越後亀紺屋>の新潟手ぬぐい【前編】
2019.10.16. Wed.
阿賀野市 越後亀紺屋 藤岡染工場
かつてはありふれた日用品のひとつだった、手ぬぐい。<越後亀紺屋 藤岡染工場>は、時代とともに暮らしから消えていった手ぬぐいの新たな魅力を引き出しています。伝統の染色技術を忠実に受け継ぎながらも、現代のターゲットに合わせたデザインを取り入れた「新潟手ぬぐい」。その製造現場を訪ねました。
新潟の柄をポップにデザイン
柿の種、トキ、長岡花火、へぎそば、茶豆など、新潟らしさがあふれる柄に染められた「新潟手ぬぐい」。そのデザインは、レトロな温もりを宿しながらも、どこかポップでかわいらしさを持っています。紺色や小豆色といった昔ながらの色だけでなく、赤、黄色、水色といった明るい色彩の柄もあって、選ぶ楽しさも味わうことができます。
1枚1,000円(本体価格)という価格も手に取りやすく、贈り物や手みやげとしてはもちろんのこと、自宅用にお買い求めになるお客さまも増えています。顔を洗った時や、台所仕事で手が濡れた時、お風呂の時など、暮らしのさまざまな場面で活躍する手ぬぐい。タオルにかわる日常の道具として、暮らしの中で何かと便利に使える道具なのです。
すべての工程を、手作業で
白鳥が飛来する阿賀野市の瓢湖。<越後亀紺屋 藤岡染工場>の店舗は、そこからほど近くの商店街に軒を連ねます。職人たちが手ぬぐいを染める工場も、その奥にあります。
最初の工程は「糊付け」。すべての工程の中で実はここが一番大事だと、藤岡利明専務は語ります。「手ぬぐいに使う生地は1ロールが20メートル。手ぬぐい1枚が90センチメートルなので、22枚取れる計算になります。工程はすべて手作業。生地を折り曲げて重ねていき、糊付けと染色をしてから、最後に裁断をします」とのこと。つまり、この工程で少しでもズレがあれば、22枚全てが失敗となってしまうのです。

▲生地の上に型枠をのせ、その上から糊付けをしていきます

▲これが糊付け前の生地。1ロールが20メートル(手ぬぐい22枚分)

▲工場内は熱気があり、ほのかに海の香りがします

▲香りの正体は、この糊。材料に「布海苔」が使われているそうです
伝統を受け継ぐ「染め」と「洗い」
糊付けの次は、いよいよ染色の行程。「やかん」と呼ばれるジョウロのような道具を使って、生地の上から染料をまんべんなく注いでいきます。これは「注染(ちゅうせん)」や「注ぎ染め(そそぎぞめ)」と呼ばれる技法で、昔から同じ柄をたくさん染める時に使われてきました。といっても、一度に染められるのは生地2ロール分、44枚だけなので、手間がかかることに変わりはありません。

▲糊付けした生地の上におがくずをかけて、乾燥させます

▲生地と生地の間の空気を抜くために、上から細かく叩きます

▲いよいよ染色。「やかん」を使い、生地に染料を注いでいきます
染料が一番下の生地まで染み込むように、台の下に設置された機械が大きな音を立てて空気を吸い込んでいきます。それでも一度ではすべて染まらないため、表と裏からそれぞれ3~4回ずつ染めるとのこと。染料は70度で、湯気が出るほどの高温。職人はヤケドをしてしまうこともあります。
どんな色に染めるのか。それを決めるのが染料の配合。現在では求められる色も多様化し、配合バランスを変えながら、色のバリエーションを増やしているそうです。
次の行程は、染料を落とす「洗い」。竹竿の先に生地をひっかけ、豪快に水の中をくぐらせます。

▲ダイナミックな動きで水の中をくぐらせると、弾ける水が小気味良い音を立てます(染色とは別の柄の手ぬぐいです)
生地を干し、乾いたら裁断して、手ぬぐいが完成します。

▲脚立を使って、手ぬぐいを干します

▲すべて職人たちの手作業によって作られていました
創業から270年。伝統の染色技法をい守りぬいてきた<越後亀紺屋>が、どのように現代の暮らしに手ぬぐいの魅力を伝えてきたのか。後編ではその物語に迫ります。
越後亀紺屋 藤岡染工場
〒959-2021 新潟県阿賀野市中央町2-11-6
電話:0250-62-2175
取材・文章・撮影:横田孝優(ザツダン)
※掲載商品は取材時のものとなり、変更となる場合はがございます。予めご了承ください。
RECOMMEND
その他のおすすめイベント