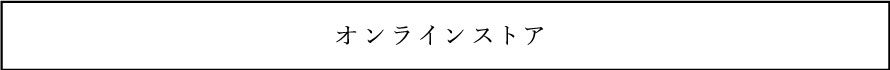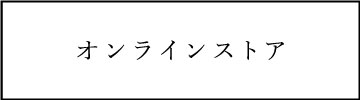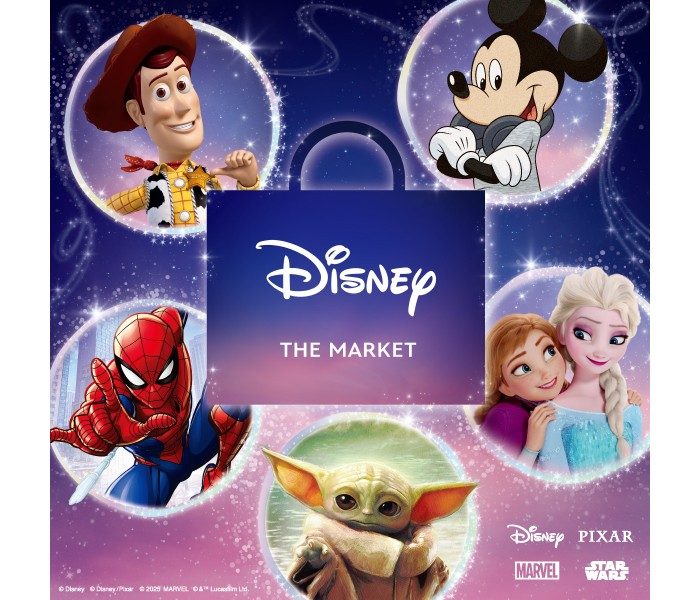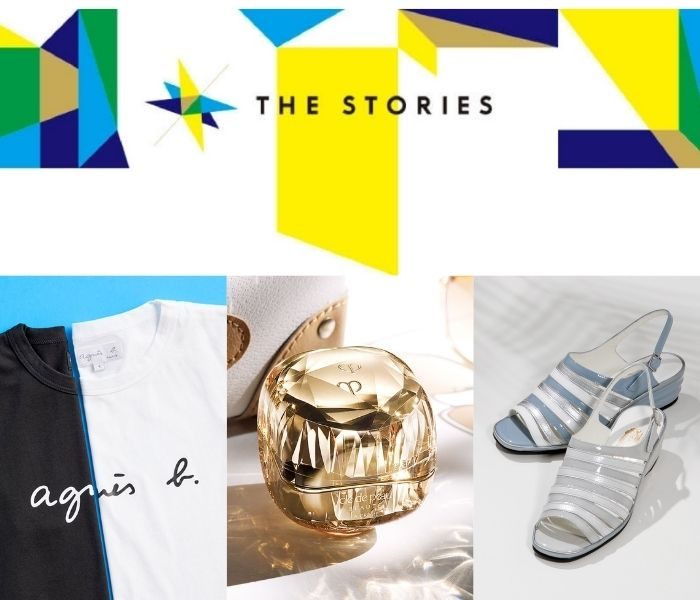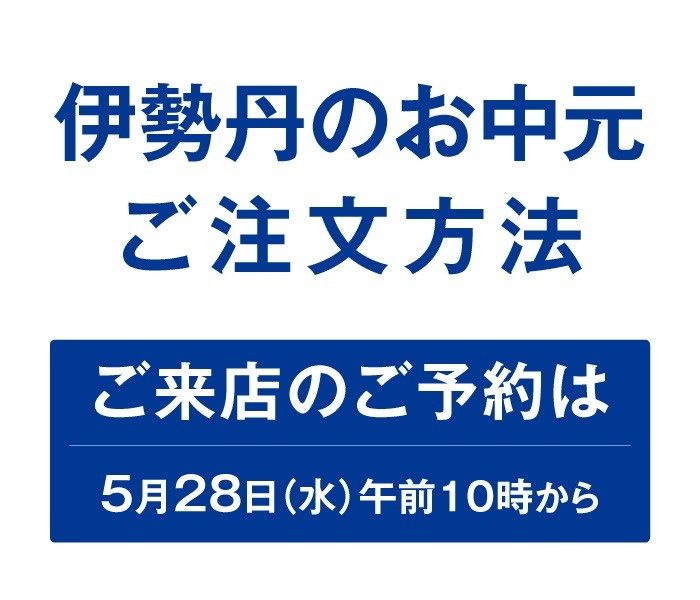一枚の布だからごまかしが利かない。生地の質を追求する〈絽紗(ろしゃ)〉のストール【後編】
2020.5.21. Thu.
五泉市 横正機業場
創業から120年、着物を染める前の「白生地」を織り続けてきた横正機業場。近代化とともに着物離れが進み、白生地のニーズも減少する中で、同社は2016年にストールの自社ブランド<絽紗>を立ち上げます。そのキーパーソンとなったのが、5代目社長の横野恒明さんと、その弟で専務の弘征さん。地に足がついたものづくりを目指す二人の思いが、白生地の可能性を広げました。
自社商品にしないともったいない
「父には継がないほうがいいと言われていたんですよ」と笑う、専務の横野弘征さん。右肩下がりの業界、しかも兄弟での経営は揉めることも多い。そんな理由から、先代社長は息子たちに会社を譲るつもりはなく、横野さんたち自身も別の道を歩んでいました。
▲ 弘征さんは元システムエンジニア
横正機業場の前身、横野工場は1900年に設立。白生地の製造で60年代までは成長を遂げてきましたが、70年代に入ると洋装化が進んで着物の需要も減少。企業規模を縮小しながら、経営を続けてきました。
一度は事業承継をしないと決めた横正機業場でしたが、父が体調を崩したことをきっかけに、2005年に兄の恒明さんが入社。経営と織物の技術を学びました。「これまで培ってきた技術を継承したい」と考えた恒明さんはベテランの職人たちと協力し、薄い絹生地の開発に着手。和装以外の可能性を模索し始めます。13年に恒明さんは社長に就任。弘征さんもそれまで働いていた会社を辞めて専務の職に就きました。
▲ 現在の従業員は13名
新事業担当の弘征さんは、会社と産地の情報発信を開始。県内クリエイターと雪だるま柄の白生地を開発する様子をフェイスブックに投稿していたところ、経済産業省の「絹のみち広域連携プロジェクト」への参加が決まります。
15年の夏、恒明さんたちがふわりとした軽い生地を完成させます。弘征さんはプロジェクトの講師に、新製品をストールの素材として販売することを相談。すると「技術が盗まれるだけ。自社で商品化しないともったいない」と叱咤されたのです。このことがブランド誕生の大きなきっかけとなりました。
三越日本橋本店のバイヤーを紹介され、ポップアップでの販売が決定。県内外の染色業者と組み、藍染めや和柄などのストールを揃えました。そして迎えた2016年3月、<絽紗>がデビューを果たします。
上手くいくのか不安を感じていた横野さんたちでしたが、結果は大好評。数回の限定販売を経て常設商品となり、新潟三越などでも販売されることになりました。
「自分たちのものづくり」を大切にする姿に共感
NIIGATA 越品では2019年6〜7月にポップアップを開催。若者からシニアまで幅広い層のお客さまに手にとってもらうことができました。バイヤーの長谷川雅史は「ニットで有名な五泉市ですが、遡っていくと白生地や養蚕といった産業が存在します。まず歴史的な観点から、横正機業場さんのものづくりは重要です」と地域産業としての価値に注目します。

▲ NIIGATA 越品でのポップアップ。頭に巻くなど、ストールの自由な楽しみ方を提案
「そして、若い経営者が兄弟で自社ブランドを立ち上げた点にも惹かれました。世の中にたくさんの商品がある中で、NIIGATA 越品が大切にしたいのはストーリーです。自分たちのものづくりを大切にしている生産者がいることを、ぜひ伝えていきたいと考えています」。

▲ 同社のベビーウェアブランド「しろずきんちゃん」のアイテムも並びました
さらなる価値を提供するために、新しい企画も準備中。「横正機業場さんが守ってきた伝統を大切にした、新しい挑戦について企画している最中です。そちらも楽しみにしていてください」と語ります。
生地を研究し、地に足がついた仕事がしたい
ブランド名の<絽紗>は、絹織物の種類である絽(ろ)と紗(しゃ)に由来。絽は、フォーマルな場にふさわしい夏の定番とされる織物。紗は、カジュアルからセミフォーマルまで幅広く用いられ、「紗がかかったような」という例えもあるように、透け感のある涼しげな織物です。ブランド名には「絹織物の魅力を伝えたい」という横野さんたちの思いが託されています。

▲ 一枚のストールの中に、着物の美しさや上品さが込められています
「ストールは一枚の布。シンプルだからこそ、良くも悪くも素材そのものの品質が出てしまう。顔や首に直接触れるものでもあり、見た目だけでなく風合いや肌触りにも同じことが言えます」という弘征さんの言葉の通り、横正機業場は質の高い白生地を作ることを重視し続けます。「やっていく中でわかったのは、染を生かす生地が必要だということ。色や柄を美しく引き立てるために、染との相性を考慮した生地を作るようにしています」。
▲ 文化やファッションの枠にとらわれずに楽しめるのも、ストールの魅力。贈り物にも使いやすい
昨年、五泉市にあった6社の織物工場のうち3社が廃業。それまでの製造量を残った会社で分担することになり、依頼や相談が増えたといいます。増加したニーズに対応するために、横正機業場は6人の従業員を雇用。3人は退職した経験者、3人は未経験者です。恒明さんは「技術を守るだけでなく未来に進んでいくために、次の技術者を育てたいですから」と前を向きます。
「薄くて軽く、夏涼しく、冬温かい。絽紗のストールは温暖化の現代に最適なもの。私たちの目標は生地を極めることです。これからも変わらず、ものづくりに真摯に向き合い、地に足がついた仕事をしていきたいです」。
<取材後記>
「友禅」「小紋」「縮」など、着物づくりで連想する言葉はどれも「染」の技術。でも、染めるためには生地が必要で、その生地にも産地や技術があるはず、というのは盲点でした。「最初、ストールを作るつもりはなかったんですよ」と語る横野さんたちは、外部の専門家と積極的に出会いを重ね、彼らからのアドバイスを取り入れることで<絽紗>を誕生させました。異業界からの転職で既成概念にとらわれなかったのがプラスになったのはもちろんですが、それだけでブランディングは成功しません。重要なのは、恒明さんと弘征さんの中に白生地への敬意と自信があったこと。自分たちの生地を生かす最善の方法を考え抜いたことが突破口を切り開いたのではないでしょうか。地に足をつけ、自分たちの強みを最大化させた上で、相性のいい他の何かとの組み合わせを模索する。まるで「白生地」と「染」の関係のようではないですか、と言ったら、ちょっと狙い過ぎですかね。
株式会社 横正機業場
〒959-1824 新潟県五泉市吉沢1-2-38
電話:0250-42-2025
取材・文章:横田孝優(ザツダン)
RECOMMEND
その他のおすすめイベント